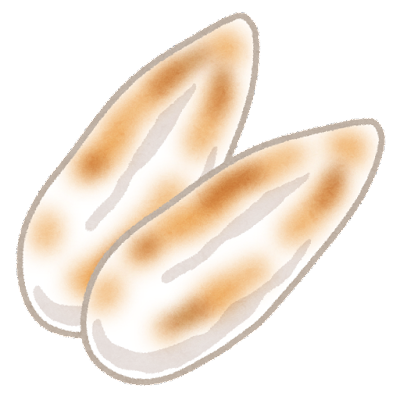今回は、東北へ移動し、
宮城県です。
早速、J-Platpatdを使って
調査しましょう。
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
(注意:2024年2月26日現在の調査結果です)
まとめに代えて本日の痒い所
- 「はらこ飯」ではヒットしませんが、「はらこ」で検索すると1件ヒットし、その商標権は、郷土料理に対して取得した商標権と思われます。
- 「笹かまぼこの磯辺揚げ」ではヒットしませんでしたが、「笹かまぼこ」で検索すると14件もヒットし、権利者の多くは、石巻市に住所又は居所があります。
- 「秋刀魚のきがき」ではヒットしませんが、「秋刀魚」で検索すると5件ヒットし、「きがき」で検索すると3件ヒットしました。いずれも郷土料理とは関係がありませんでした。
はらこ飯

はらこ飯のイメージ(サケがメインのイメージで)
宮城県には北上川、鳴瀬川、阿武隈川をはじめとする大小さまざまな河川があり、毎年秋になるとサケが産卵のために遡上する。そのため、白サケ類の漁獲量は全国トップクラス。100年以上も前から人工ふ化放流事業を行うなど、サケを守り育ててきた歴史がある。現在も県内に20ヶ所のふ化場があり、増殖と資源保護の努力が続けられている。
そんな宮城で、サケを使った郷土料理として最も有名なのが「はらこ飯」。これは、伊達政宗公が荒浜の運河工事を視察した折に、領民から献上されたことでも有名だ。「はらこ」とはこの地方でいくらを指す言葉で、サケの腹にいる子「腹子」からそう呼ばれるようになったという。
政宗公に献上する以前から、阿武隈川に遡上してくるサケを地引網で獲っていた地元の”漁師飯”として食されていた。各家庭によって味付けが異なるため、亘理では「うちのが一番」が合言葉になっている。
現代では煮上げたサケ、サケの煮汁で炊いた米、煮汁にくぐらせたいくらをそれぞれ盛り付けるが、昔はすべてを混ぜ合わせた「混ぜご飯」だったという。現在つくられているはらこ飯とは違ってシンプルな見た目だが、荒浜婦人会では、この元祖の味を伝承するべくさまざまな活動を行っている。
はらこ飯 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)
Jplatpatで検索してみると、
「はらこ飯」ではヒットしませんが、
「はらこ」で検索すると、
1件ヒットします。
第5682976号
平成26(2014)年 2月 13日に出願され、
平成26(2014)年 7月 4日に登録。
標章は、「みねちゃんのはらこめし」
との文字から構成されます。
指定商品は、はらこめしの素、
はらこめし等です。
これはまさに、郷土料理に対して
取得した商標権と言えるでしょう。
標章には「みねちゃんの」との
文字がありますので、普通名称
ではなく、造語でしょう。
識別力ありですね。
笹かまぼこの磯辺揚げ
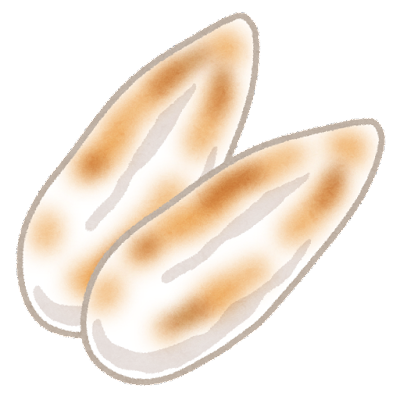
笹かまぼこのイメージ
豊かな漁場を持つ宮城県では、気仙沼や石巻、塩竈、閖上といった漁港がある、明治の中頃からヒラメやスズキ、タイなどの魚が大量に獲れるようになったものの、今ほど輸送方法も発達していない時代にあっての保存方法として生まれたのが、「焼きかまぼこ」だった。それまでは各家庭で白身魚をすり身にして、手のひらでかたどって竹串に刺して焼いていたものが、加工品として出回るようになった。当時は「手のひらかまぼこ」や「ベロかまぼこ」などの呼び名もあったが、旧仙台藩主伊達家の家紋「竹に雀」の笹にちなみ「笹かまぼこ」と呼ぶようになり、昭和に入って「笹かまぼこ」に統一された。
その後、ヒラメなどの漁獲量が激減したため、現在ではその代用品としてスケソウダラなどの白身魚が原料となっている。漁船内で活きのよいところをすり身にし急速冷凍したものが主流となっている。
淡泊な味わいで、良質のたんぱく質を含み、しかもカロリーが低いことからヘルシーな食材としても人気が高まっている。
近年では、包装技術の向上や輸送速度の向上もあり、笹かまぼこは宮城県を代表する名産品、土産品として多くの人に好まれている。県内に大小合わせて40軒以上もあるメーカーは、各々アイデアをしぼった商品を多数販売している。そのまま食べるほか、かき揚げ、おでん、天ぷらなどのアレンジメニューで食されることもある。
笹かまぼこの磯部揚げ 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)
Jplatpatで検索してみると、
「笹かまぼこの磯辺揚げ」では
ヒットしませんが、
「笹かまぼこ」で検索すると、
14件もヒットします。
さすが、郷土料理!
いずれの権利者も、
住所、居所は、宮城県です。
宮城県の中でも、
石巻市が一番多そうです。
第1046101号
第1252780号
第2671369号
第4458827号
第4458828号
第4458829号
第4458831号
第5173355号
第5573468号
第5746175号
第5803656号
第6232063号
第6463051号
第6689299号
権利者で見てみると、
株式会社白謙蒲鉾店
がもっとも多くの権利を
保有していそうです。
株式会社白謙蒲鉾店
https://www.shiraken.co.jp/corporate/
第4458827号
第4458828号
第4458829号
の連番になっている商標権、
共通とするベース構図があり、
チーズ入り
ねぎ入り
○○入りの記載なし
の3パターンがあります。
○○入りの記載なしの場合は、
指定商品が「焼きかまぼこ」
となっています。
なお、
「チーズ入り」の文字がある標章の
指定商品は、「チーズ入り焼きかまぼこ」
「ねぎ入り」の文字がある標章の
指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」
です。
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができません。
「チーズ入り」の文字がある標章なのに、
指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」で、
チーズが入っていないとか。
「ねぎ入り」の文字がある標章の
指定商品は、「焼きかまぼこ」で、
ねぎがはいっていないとか。
「焼き」の文字がない標章なのに、
指定商品が「焼きかまぼこ」の場合は
どうなるでしょうか?
商標審査基準を見てみると、
(例1) 本号に該当する場合
商品「野菜」について、商標「JPOポテト」
(解説) この場合、商標が表す商品の品質は、「普通名称としてのじゃがいも」であることから、指定商品「野菜」とは関連する商品であり、また、指定商品中「じゃがいも以外の野菜」が有する品質とは異なることから、本号に該当すると判断する。なお、指定商品「じゃがいも」と、商品の品質等の誤認を生じさせることなく 適正に表示されている場合はこの限りでない。
(例2) 本号に該当しない場合
① 商品「自転車」について、商標「JPOポテト」
(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「普通名称としてのじゃがいも」 とは関連しない指定商品「自転車」であることから、本号に該当しないと判断する。
② 商品「イギリス製の洋服」について、商標「JPOイギリス」
(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「生産地としてのイギリス」と指定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。
③ 役務「フランス料理の提供」について、商標「JPOフランス」
(解説) この場合、商標が表す役務の質である「料理の内容としてのフランス」と指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。
商標審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
とのことです。
標章の構図は、ご確認いただきたいと
思いますが、本号に該当しない場合②③
のケースなのかなと思います。
みなさんはどうお考えでしょうか?
そういえば、あたらしい商標審査基準が
令和6年4月から適用されます。
www.jpo.go.jp
秋刀魚のきがき

秋刀魚のイメージ
気仙沼の本吉地方では、昔からカツオの魚群が沿岸近くまで回遊し、大量に水揚げされていた。大抵は塩蔵ガツオとして流通していたが、その塩蔵カツオの漬け汁を「きがき」と呼んだ。この漬け汁を樽に入れて調味料として売り歩いていた業者がおり、それで大根などを煮るととても美味しいと評判になった。
「きがき」は秋田のしょつるやタイのナンプラーと同じ魚醤の一種で、当時は画期的な調味料だった。その後、イカの塩辛や塩漬けの魚をだしに大根を煮たものを「きがき」と呼ぶようになり、サンマなどの鮮魚も煮るようになった。かつては家庭の調味料といえば、自家製の味噌と塩、酢くらいだったので祝い事があれば、味噌を漉した「みそだれ」を醤油の代用品としていた。
明治時代になると、醤油は地方でも販売されるようになり、醸造業も発達した。しかしながら醤油は高価なためもっぱら祝い事や来客用だったという。
現代では、魚醤ではなく醤油でサンマを煮つける。
サンマのきがき 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)
Jplatpatで検索してみると、
「秋刀魚のきがき」では
ヒットしませんが、
「秋刀魚」で検索すると、
5件もヒットします。
うち2件は、権利者名に
「秋刀魚」の文字が・・・。
深セン市十月的秋刀魚電子商務有限公司
中国企業ですね。
そのほかの商標登録は、
第6021784号
平成29(2017)年 5月 31日に出願され、
平成30(2018)年 2月 23日に登録。
標章は、「秋刀魚の極」との文字。
指定商品は、さんまの缶詰等です。
第6262639号
平成31(2019)年 4月 16日に出願され、
令和2(2020)年 6月 24日に登録。
標章は、「鎮守府秋刀魚祭り」との文字。
指定商品は、コンピューター用プログラム等。
これは、なかなか思いつかない組み合わせ、
普通名称とは言えないですね。
第6660235号
令和3(2021)年 12月 29日に出願され、
令和5(2023)年 1月 10日に登録。
標章は、布生地を背景に多角形のような形状で
青い縁取りがされています。その中に、
「秋刀魚」「ゲランド塩」と二段書きで、
青文字で記載されています。他にも、
英文字や秋刀魚の絵、オリーブの葉のような
ものも青色で描かれています。
指定商品は、
地理的表示「セル・ドゥ・ゲランド」で保護された塩を使用した塩漬けの魚(さんま)等
とあります。
もう文字ではないので、
標準文字とは言えませんね・・・。
一方、「きがき」で検索すると、
3件ヒットします。
第5318182号
平成21(2009)年 2月 6日に出願され、
平成22(2010)年 4月 23日に登録。
標章は、「ききがきすと」「KIKIGAKIST」
の文字が二段書きされています。
指定商品は、印刷物等
指定役務は、技芸・スポーツ又は知識の教授等
です。
二段書きされていると、識別力が
より出ますね。
というよりは、指定商品等から考えが及びにくい
標章になっていると思います。
あと、「きがき」の文字が標章の中に埋もれている
印象を持ちました。
第5353636号
平成21(2009)年 12月 7日に出願され、
平成22(2010)年 9月 17日に登録。
標章は、「きがきく」「きのこ」と二段書きされ、
キノコのイラストも記載されています。
指定商品は、生キノコです。
二段書き、イラストが識別力となっていると
思われます。
第5704482号
平成24(2012)年 12月 14日に出願され、
平成26(2014)年 9月 26日に登録。
標章は「きがきくかぐ」の標準文字から
構成されています。
指定商品は、椅子等の家具ですね。
「かぐ」の文字が標章に含まれていますが、
「きがきく」が接頭語、
「かぐ」が接尾辞、
となり、一つの造語になっています。
これでは、なかなか普通名称とは
言えませんね。
編集後記
なす炒り
なすの旬は夏から秋であり、地域によって育てられている種類もまったく異なる。
宮城県でなすの栽培がはじまったのは、伊達政宗公の時代、1590年ごろではないかといわれている。伊達家家臣の一人が博多から持ち帰ったなすが、長い年月をかけて東北の気候になじみ、独特のかたちになったと考えらている。それが「仙台長なす」で、漬物にしたり、炒め物にしたりと様々な料理に用いられている。
なす炒り 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)
マーボー焼きそば
以下の3点を、仙台マーボー焼そばの条件としている[1]。
麻婆を使い、具は豆腐に限定しない。
麺は焼くか、揚げたものとする。
宮城県中華飲食生活衛生同業組合の認定人が認定したものとする。
2015年現在、宮城県内49店舗(内、仙台市内42店舗)が仙台マーボー焼そばを提供する店として認定されている。
仙台マーボー焼そば - Wikipedia
油麩丼(あぶらふどん)
お盆になると豆腐店は精進料理に使用する油揚げ、豆腐づくりに精を出した。しかしながら今のような冷蔵技術がなかった時代は、油揚げも豆腐もすぐに傷んでしまうのが大きな課題だった。そんな中、明治の末期に登米の豆腐店が考案したのが油麩だった。
小麦粉と水を合わせて練り、それを水ででんぷんを洗い流すとグルテンが残る。
麩は生麩と焼き麩、油麩があるが、生麩はグルテンにもち米粉を合わせて蒸したもの、焼き麩はグルテンに小麦粉を合わせて焼いたもの。油麩は、焼き麩と同じくグルテンに小麦粉を加えたもので、棒状にしたものを油で揚げる。油で揚げているので香ばしく、歯ごたえもあるので、ベジタリアン料理やマクロビ食としても重宝されている。登米地方だけで生産されていたが、全国的にその美味しさが広まると、登米以外でも大量に生産されるようになった。
油麩丼はその油麩を使った代表的な料理で、地元の旅館のおかみが考案したメニュー。かつ丼のかつの代わりに油麩を使用するもので、油麩の風味が存分に生かされている。「B-1グランプリ」にも参加したことで、全国的にも知られている。
油麩丼 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)
本日までの調査進捗

本日までの調査進捗
白地図ぬりぬり-地図グラフの制作ツール (freemap.jp)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
宮城県の郷土料理・ご当地グルメと商標の雑談はいかがでしょうか。

リッキー