さて、今回からは、
プログラムの著作物へ
話題を移しましょう。
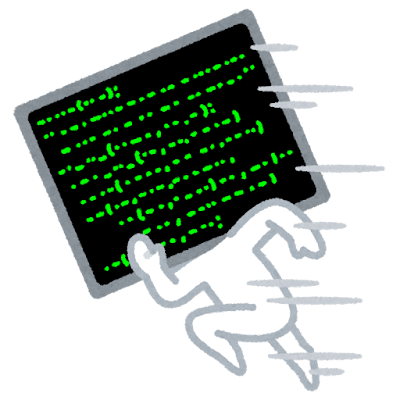
著作物は下記に分類
されますが、
言語の著作物(1号)
音楽の著作物(2号)
舞踏の著作物(3号)
美術の著作物(4号)
建築の著作物(5号)
図形の著作物(6号)
映画の著作物(7号)
写真の著作物(8号)
プログラムの著作物(9号)
編集著作物(12条)
データベースの著作物
二次的著作物
「プログラム」、
「データベースの著作物」
が特殊な感じがしますね。
情報化の進展とともに、コンピュータ・ソフトウェアなかんずくのプログラムの重要性が増してきた。プログラムがハードウェアの付属物であった時代には、プログラム自体の法的保護の必要性は低かったが、ハードウェアと切り離されてプログラムが独立した財として価値を有するようになると(アンバンドリングと言われている)、プログラム自体の法的保護が必要となり、その方法を巡って大論争が生じた。具体的には特許法的アプローチと著作権法的アプローチの対立であった。
(中略)
結局、アメリカからの強い圧力もあり、通商産業省は新規立法を断念し、昭和60年にプログラムを著作物と認める著作権法改正が成立した。そしてプログラムを著作権法で保護するという点については現在では国際的に決着がついており、この論争に一応の終止符が打たれた。プログラムのようなものが著作権法システムに馴染むものか否か、という点について疑問はあるものの、著作権法が改正されてプログラムを取り込んだ以上、著作権法の枠内でいかにして妥当な解釈をすべきか、更にはプログラムをも飲み込んだ著作権法の体系をいかに再構築すべきか、という議論が必要となろう。
プログラムの異端な感じが
伝わってきますね。
ただ、プログラムを著作物
とするのは国際調和にかなう
もののようです。
著作物の定義は
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
でした。
プログラムの著作物は、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲
のうち、学術の範囲に属する
ようです。
4つの中では一番
しっくりくると思います。
プログラムが著作物であるためには著作物の一般的要件を満たす必要がある。プログラムであればほぼ学術的といえようが、個性については問題がある。プログラムの著作物に要求される創作性の概念を、美術・音楽・小説の場合と同一に考えるべきか否かという点については議論があるところであるが、プログラムについても、他の著作物と同様に、創作者の何らかの個性が現れていれば足りると、一般的には考えられている。しかしながら、プログラムについては人格的な意味での個性は考えにくく、選択の幅という考え方が最も妥当する分野であろう。プログラムによっては選択の幅が極端に狭い場合や、ごくありふれている場合、誰が作成しても同じあるいは類似のものとなるようなプログラムの場合には創作性が否定されることになろう。多くの判決においては、一般論は別としても、あてはめの箇所では選択の幅が実質的に決め手になっているように思える。
こちらでも、
プログラムの著作物は、
学術の分野に属する
ことが確認できました。
異端な感じの
プログラムと
既存の著作物が
どう取り扱われるのか?
気になるところでは
ありますね。
意外にも、
「選択の幅」という
共通の判断手段が
使えそうとのことです。
そして、判例でもよく
見かける言葉ですよね。
昔の判例を熟知出来て
いませんが、判例を
研究すると、
「選択の幅」が
よく出てくるという
潮目が分かる時が
ありそうですね。
新しい創作性の概念として
下記の記載があります。
新たに統一的創作性の概念を確立するならば、それは現在における著作権法の趣旨から導く以外にない。著作権法の目的は文化の発展にあるが(1条)、既に縷々述べた通り、著作権法の構造から、文化の発展とは思想・感情の表現である情報の豊富化にあると考えるべきである。情報の豊富化が著作権法の目的であるとするならば、その趣旨に従い、創作性の概念を、「思想・感情の流出物」としての個性ではなく、「表現の選択の幅」と捉えるほうが妥当であろう。すなわちある作品に著作権を付与しても、なお他のものには創作を行う余地が多く残されている場合に、創作性があると考えるべきである。つまり作品それ自体のみで創作性を判断するべきものではなく、他者の行為可能性と関連において判断されるべきである。そのような考え方は、単に表現の豊富化に資するという著作権法の理念に合致するだけなく、「表現の自由」という憲法の理念にも合致するものである。
(中略)
表現の多様性こそ、著作権法の究極の目的と言えよう。このような観点からも、創作性を「表現の選択の幅」と捉えることは有意義であると考える。
(以下省略)
著作権法の目的に、
文化の発展とあります。
文化の発展とは
思想・感情の表現である
情報の豊富化にある
という考え方もできる
のですね。
こうした場合に、
「表現の選択の幅」
がなんともうまく
合致する。
誰がこのように仕組んだ
のでしょうか。
たまたまなのでしょうか?
上手くあてはまっている
気がします
まとめに代えて本日の痒い所
- プログラムが著作物の一例に含まれているのには異端な感じがする
- プログラムが著作物に含まれるようになったのは、外圧(国際調和)である
- プログラムが著作物に含まれるようになり、創作性の概念に変化が必要であったが、結果、より著作権の法目的に叶う新しい創作性の概念が誕生した
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週も著作権の雑談はいかがでしょうか?

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★