特許出願をしようと考えたときに、特許出願して権利化しようか、特許出願して権利化せずに後願排除しようか、秘匿しようか、など考えると思います。みなさんは、何をどう考えるでしょうか?
ブロックチェーンやAIなど最新技術について出願したわけではないのですが、出願に当たり、こんなことを考えたってことをシェアさせていただきたいと思います。今回は、特許出願して権利化しようか、特許出願して権利化せずに後願排除しようか、秘匿しようか、ではなく、違うことで頭をひねっていました。
長めですが、お付き合いいただけると嬉しいです。
あと、今までYOと名乗っていましたが、イニッシャルっぽいので違うのに変えてみました。今日からは、リッキーと改名して、新たな気持ちでブログを書いていきたいと思います!
[前提1]
・ある技術分野で、高速な処理に必要な発明Aを特許出願Aすることになった
・自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった
・発明Aに続いて、発明B、発明C、発明D・・・と後続の発明が後に控えている
・発明B、発明C、発明Dは、特許出願Aの出願日の6か月後に提案される
1.先行技術は本当にないのか?
前提に、「自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった」としていました。事実、見つけられなかったのですが。
そして、「発明Aに続いて、発明B、発明C、発明D・・・と後続の発明が後に控えている」ので、発明Aについて間違った判断をしたまま、発明Bについて特許出願B、発明Cについて特許出願C、発明Dについて特許出願D・・・と別に特許出願をすると、共倒れになる危険性もありました。
例えば、
・引用文献1により発明Aが新規性なし
・引用文献1+引用文献2により発明Bが進歩性なし
・引用文献1+引用文献3により発明Cが進歩性なし
・引用文献1+引用文献4により発明Dが進歩性なし
最悪ですね・・・4件の出願が全部権利化できない。想像もしたくないです。
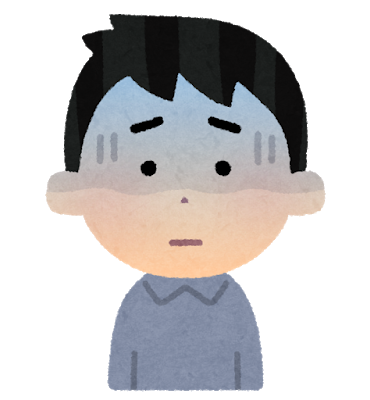
そこで考えたのが、もう審査してもらって白黒をさっさとつけてしまおうということです。特許出願Aをして発明Aに新規性がない、進歩性がない、または、進歩性あり、がはっきりすれば、特許出願B、特許出願C、特許出願Dについてどう出願するべきかが考えられるからです。
特許出願B、特許出願C、特許出願Dについてどう出願するべきかが考えるためには、審査結果が早く欲しい。さて何が考えられるか。
2.早く審査結果を得る方法
まず、特許出願Aをしただけでは、審査官により発明Aについて、新規性、進歩性の判断がなされないことはご存じかと思います。諸外国ではそうでもないですが、日本では、審査を受けるために、出願審査請求をしなければなりません(特許法48条の3)。
特許庁不断の努力により、審査はスピーディーになり出願審査請求をしてから約11か月で最初の拒絶理由通知が来るまでに審査スピードが向上しています。とてもありがたいことです。

しかし、発明B、発明C、発明Dが提案されてから5か月しないと早くても発明Aに対する拒絶理由通知が来ません。これでは、5か月間、待たなくてはなりません。競合も居ることですから、悠長に待っていることはできません。
それでは、出願審査請求から11か月よりも早くに拒絶理由通知を受けるにはどうしたらよいか。下記の3つが考えられます。
①優先審査
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明をしていると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる(特許法48条の6)。
②早期審査
2017年の実績では、早期審査の申請から平均3か月以下で審査結果が得られると、特許庁HPにて記載されています。ただし、早期審査の対象になる出願は、(1)実施関連出願、(2)外国関連出願、・・・等に限られています。
③スーパー早期審査
利用されて特許査定されると、ニュースで報道されることもありました。記憶は定かではないですが、スーパー早期審査の請求から4日?8日?ぐらいで、特許査定されたという案件があったと記憶しています。ただし、スーパー早期審査の対象になる出願は、(1)実施関連出願かつ外国関連出願、・・・等に限られています。早期審査よりもさらに対象が限定されています。
3.どれを選ぶか
①優先審査
出願公開が一つの要件になっていますが、出願公開は特許出願の日から1年半以降に公開されます(特許法64条)。ただし、出願公開請求(特許法64条の2)を行えば、特許出願の日から1年半未満でも出願公開されるので、出願公開の要件を満たすことはできます。しかし、特許庁長官に「必要がある」と認められないと、優先審査の対象にはなりません。
②早期審査
早期審査の対象になる出願は、(1)実施関連出願、(2)外国関連出願、・・・等に限られているので、実施関連出願の要件を満たす場合、実施関連出願ではないかと競合に目を付けられやすくなります。出願日と登録日を見てみれば、その期間の長さで早期審査したかどうかは簡単に見分けがつきます。また、外国関連出願の要件を満たそうとすると、翻訳に時間がかかりそうにも思えますが、例えば、日本語で米国出願をしておいて後から翻訳文を提出できますから、この要件を満たすことができそうです。米国代理人の費用が高いので、そこがネックですが。
③スーパー早期審査
スーパー早期審査の対象になる出願は、(1)実施関連出願かつ外国関連出願、・・・等に限られているので、満たさなければならない要件が増えるのでハードルが高いですが、早期審査と同じように考えることができます。
4.新たな前提
どれを選ぶか整理できたところで、新たに考えなければならない前提が出てきました。
[前提2]
・発明B、発明C、発明Dに続いて、発明E、発明F、発明G・・・と後続の発明がさらに出てくる気配(発明Aをしてから1年後を想定)
特許査定がなされると(特許法第51条)、特許権取得のために特許料を納付しなければなりません(特許法107条)。特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、特許公報に発明が掲載されます(特許法66条)。
発明B、発明C、発明Dについても懸念されますが、特許権を取得するとその発明は公開されてしまいます。公開されるということは、発明Aが、ほぼ確実に発明E、発明F、発明Gの先行技術となり、新規性、進歩性を審査する際の先行技術になります。また、公開の時期にもよりますが、発明Aが、発明B、発明C、発明Dの先行技術となり、新規性、進歩性を審査する際の先行技術にもなる場合があります。
発明Aが公開されていない状況で、審査を受ければ、発明Aを先行技術としない分、新規性、進歩性の審査において新規性あり進歩性ありと言われやすくなることは言うまでもありません(発明Aよりも発明B~Gに近い先行技術がないという前提です)。
5.振出しに戻る
発明E、発明F、発明Gの存在が認識され始めたので、「自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった」という懸念よりも、「発明E、発明F、発明Gを競合よりも先に出願できるか」ということが懸念点となりました。
「発明E、発明F、発明Gを競合よりも先に出願できるか」ということが懸念点であれば、特許出願Aの日から1年半までの期間、競合に発明Aの存在を知られないようにすることが発明E、発明F、発明Gについて権利化するうえで有利に働くかもしれません。
でも、「自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった」という懸念は払しょくされていません。
6.まとめ
まとまらないじゃんってのが、正直なところではありますが。
「自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった」よりも、「発明E、発明F、発明Gを競合よりも先に出願できるか」に比重があれば、特許出願Aの日から1年半までの期間を思う存分使って、発明をしたらよいことになります。
また、「発明E、発明F、発明Gを競合よりも先に出願できるか」よりも、「自己の先行技術調査では、新規性、進歩性を否定することのできる先行技術を見つけられなかった」に比重があれば、優先審査、早期審査、スーパー早期審査、の活用を検討したらいいのかと思います。権利化以外のコストが発生してしまいますが、コスト次第で、調査会社に依頼して、先行技術を探すのも手かもしれません。そもそも、発明B~Gを進歩性がでるように熟考しろ!と言われればそれまでなのですが。
他の手もあるよってことで、ブログ等を使って発信してもらえたら、参考にさせていただきたいです。
